- 子どもが勉強せず、親としてどう対応すればいいのか知りたい
- 勉強のモチベーションを上げる方法を知りたい
- イライラを抑える方法を知りたい
高校生のお子さんをお持ちの保護者の方。
「子供が勉強しなくてイライラする…」と感じていませんか。
しかし、高校生が勉強しないのには理由があります。
★この記事を書いた人
- 現役の士業。数々の難関試験(行政書士、社労士など)に合格。
- 小学校、中学校の教員免許をもち、教師歴10年以上の現役教師が監修。
そこでこの記事では、高校生が勉強しない理由やそのリスク、親ができる対応策を解説します。
「勉強しない子ども」にイライラするのではなく、子どもが自ら学びたくなる環境を作る方法を考えていきましょう。
オススメNO.1の家庭教師は「家庭教師のトライ」。
- 指導実績147万人
- 登録教師数33万人
- 顧客満足度NO.1
まずは資料請求(無料)して詳細をお確かめください(30秒で入力完了)
なぜ高校生は勉強しないのか?

高校生の子どもが勉強しないと不安になってしまいますよね。
ただ「勉強しなさい!」と叱るだけでは、逆に反発を招くこともあります。
まずは、なぜ勉強しないのかを理解することが大切です。
高校生が勉強しない主な理由

高校生が勉強しない理由は一つではなく、さまざまな要因が絡み合っています。
主な理由として、
- 勉強が苦手
- やる気が出ない
- 環境が整っていない
- 生活スタイルの影響
などが挙げられます。
まず、勉強が苦手・嫌いという理由です。
授業についていけなかったり、理解できない内容が増えたりすると、勉強に対する苦手意識が強くなります。
≫参考:【高校生必見】テストで0点を取ったらどうなる?進級・成績への影響と対策
次に、モチベーションの低下も大きな要因です。
「勉強しなさい」と言われるほど反発したくなるのが高校生の心理。
- 「勉強する意味がわからない」
- 「将来の目標が決まっていない」
など、目的意識が持てないとやる気も起きません。
また、スマホやゲームの誘惑、部活や友人関係のストレスなども影響します。
勉強より楽しいことが身近にあれば、そちらを優先してしまうのは自然なことです。

勉強しない高校生が直面するリスク

高校生が勉強しないことで、将来的にどのような影響があるのでしょうか?
短期的には、
- 「テストの点が悪い」
- 「授業についていけない」
などの問題が出てきますが、長期的には進路の選択肢が狭まるなどのリスクもあります。
まず、学力の低下による自信喪失が挙げられます。
テストの点数が悪いと「自分は勉強ができない」と思い込み、さらにやる気を失ってしまう悪循環に陥ります。
次に、進級や卒業が危うくなる可能性もあります。
成績が伸び悩むと、必要な単位を取れず留年になるケースも。
また、希望する進学先があっても、必要な学力が伴わなければ志望校の選択肢が狭まってしまいます。
さらに、将来の選択肢が減ることも大きなリスクです。
高校生のうちは進路について実感が湧かないかもしれません。
学力不足が原因で「本当はやりたかった仕事に就けない」と後悔することもあります。
≫参考:勉強できない高校生の進路は?高校生が知るべき5つの選択肢
高校生のやる気を引き出す9つの極意
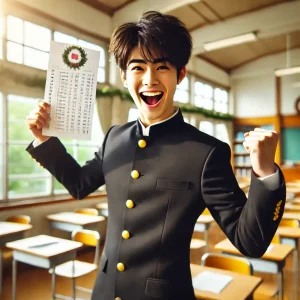
高校生が勉強しないと、親としてはつい叱ったり強制したりしたくなります。
しかし、無理に勉強させようとすると、逆に反発を招きやすいものです。
ここでは、高校生のやる気を引き出す9つの方法 を紹介します。
1. 子どもの自主性を尊重する
強制されると反発するのは自然なことです。
「勉強しなさい!」と命令するのではなく、自主的に机に向かえるような環境を整えることが重要です。
2. コミュニケーションを大切にする
子どもが勉強しない理由を知ることが大切です。
悩みや不安があれば、まずは話をじっくり聞き、共感しながら解決策を一緒に考える姿勢を持ちましょう。
3. 勉強しやすい環境を整える
リビング学習が向いている子もいれば、一人で静かな環境の方が集中できる子もいます。

4. スマホやゲームの管理を工夫する
「スマホ禁止」と決めるのではなく、時間の使い方を一緒に考えることが大切です。
スマホの利用時間を制限するのではなく、「勉強が終わったら自由に使える」といったルールを作るのも効果的です。
5. 小さな目標を設定する
いきなり「テストで90点取ろう」と言われても、やる気は出ません。
「今日は英単語を10個覚える」など、達成しやすい目標を設定することがポイントです。
6. 適度な声かけをする
- 「頑張ってるね」
- 「少しずつでもいいよ」
といったポジティブな声かけ が、やる気を引き出します。
否定的な言葉ではなく、励ましの言葉を意識しましょう。
7. 勉強の意味を一緒に考える
「勉強する意味がわからない」と感じる高校生も多いものです。
- 「将来の夢を叶えるため」
- 「好きなことを学ぶため」
など、子ども自身が納得できる理由を一緒に見つけることが大切です。
8. ご褒美や罰でコントロールしない
「テストで80点取ったらお小遣いアップ」といったやり方は、一時的な効果はあります。
しかし、長期的な学習習慣にはつながりにくいため注意が必要です。
9. 親自身が学ぶ姿勢を見せる
親が本を読んだり、新しいことを学んだりする姿を見せることで、「勉強は大人になっても必要なもの」と伝えることができます。
家庭教師の活用を検討する

高校生の子どもが勉強しないと、親はどうしてもイライラしてしまいますよね。
親が直接言ってもなかなか伝わらないことが多いものです。
そんな時は家庭教師の力を借りましょう。
1. 子どもに合った勉強方法を提案してくれる
家庭教師は、一人ひとりの学力や性格に合わせた指導をしてくれます。
学校の授業が分からない場合でも、つまずきの原因を見つけ、理解しやすい方法で教えてくれます。
2. 勉強の習慣が自然と身につく
「勉強しなさい!」と言われると反発する子でも、家庭教師が来ると決まった時間に机に向かう習慣がつきやすくなります。
また、親ではなく第三者の先生からアドバイスを受けることで、素直に聞き入れやすいというメリットもあります。
3. 苦手な科目を重点的に対策できる
学校の授業はクラス全体のペースに合わせて進むため、分からないまま放置されることもあります。
しかし、家庭教師なら苦手科目を重点的に対策でき、子どもの理解度に合わせたスピードで進められます。
4. 親のストレスが減る
「勉強しなさい」と言い続けるのは親にとってもストレスです。
家庭教師をつけることで、勉強のサポートをプロに任せられるため、親子関係のギスギスした雰囲気を改善できます。
5. 受験対策にも強い
高校生になると、定期テストだけでなく大学受験も視野に入れる必要があります。
家庭教師は受験対策にも精通しており、志望校に合わせた戦略的な勉強法を教えてくれるので、効率よく学力を伸ばせます。
オススメは家庭教師のトライ

数ある家庭教師のなかで最もオススメなのは家庭教師のトライです。
名前を聞いたことがある方も多いのではないのでしょうか。
家庭教師は登録教師数33万人※を誇ります。
※講習会を受講している教師数(2024年3月31日時点。)
★家庭教師のトライの特徴
- 147万人以上※の指導経験に基づく独自の学習法
- 最先端のAIを組み合わせて、効率よく成績向上
- 対面指導はもちろん、オンライン指導も対応
- 全国どこでも受講可能
※これまでにトライに入会された生徒数(2024年3月31日時点。大人の家庭教師を除く)。
トップクラスの指導力と合格実績が最大の魅力です。
苦手克服はもちろん、志望校の合格に特化した対策など様々な要望に対応!
家庭教師を選ぶなら、「顧客満足度が全国No.1(2025年 オリコン顧客満足度®調査 家庭教師 第1位)」のトライからご検討ください。
まずは資料請求して、詳しい内容をお確かめください。
人間力を育てる視点からのアプローチ

勉強の習慣をつけることは大切ですが、それ以上に「学ぶ力」や「生きる力」を育てることも重要です。
単なる学力向上ではなく、将来に役立つ人間力を育てる視点からアプローチすると、結果的に勉強への意欲も高まります。
1. 論理的思考力を鍛える
勉強が苦手な子でも、日常の会話の中で「なぜそう思うの?」と問いかけるだけで、考える力を伸ばすことができます。
また、読書やディスカッションを通じて、言葉で説明する力を養うのも有効です。
2. 自己管理能力を高める
計画を立てて実行する力は、勉強だけでなく社会に出ても役立ちます。
「今日やることを3つ決める」など、小さな目標を設定する習慣をつけると、自然と勉強の計画も立てやすくなります。
3. 好奇心を引き出す
子どもが興味を持ったことを一緒に深掘りすることで、「学ぶことは楽しい」と感じやすくなります。
勉強を強制するのではなく、知ることの面白さを伝えることが、学習意欲を高める第一歩になります。
【まとめ】勉強しない高校生にイライラする親必見!
高校生が勉強しないと、つい焦ってしまうものですが、無理に勉強を強制しても逆効果です。
大切なのは、子ども自身が「なぜ勉強するのか」を理解し、前向きに取り組めるようサポートすることです。
まずは、子どもの気持ちに寄り添い、勉強しない理由をしっかり把握しましょう。
そして、自主性を尊重しながら、環境を整えたり、モチベーションを高めたりする工夫を取り入れることが重要です。
小さな成功体験を積ませることで、「できるかも」という自信が生まれ、やる気につながります。
また、勉強だけにとらわれず、論理的思考力や自己管理能力を育てる視点も大切です。
将来の選択肢を広げるためにも、親ができるサポートを続けていきましょう。
焦らず長い目で見守ることで、子ども自身が勉強と向き合うタイミングをつかめるはずです。
≫参考:【徹底比較】おすすめ家庭教師ランキングベスト3!選び方のポイントも解説
関連記事

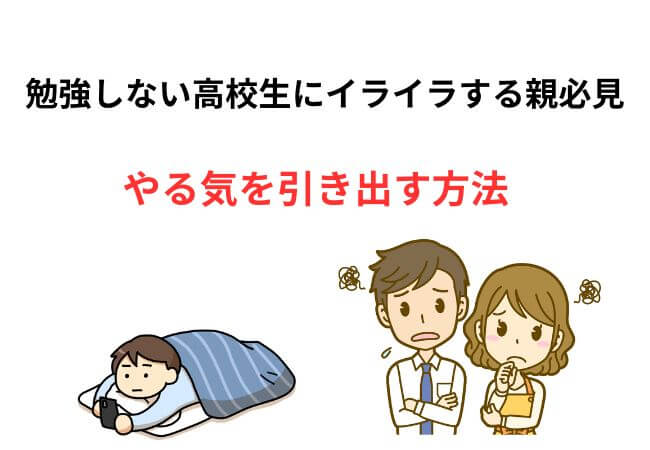


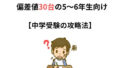
当サイトはリンクフリーです。管理者の許可なくリンクを貼っていただいても構いません。